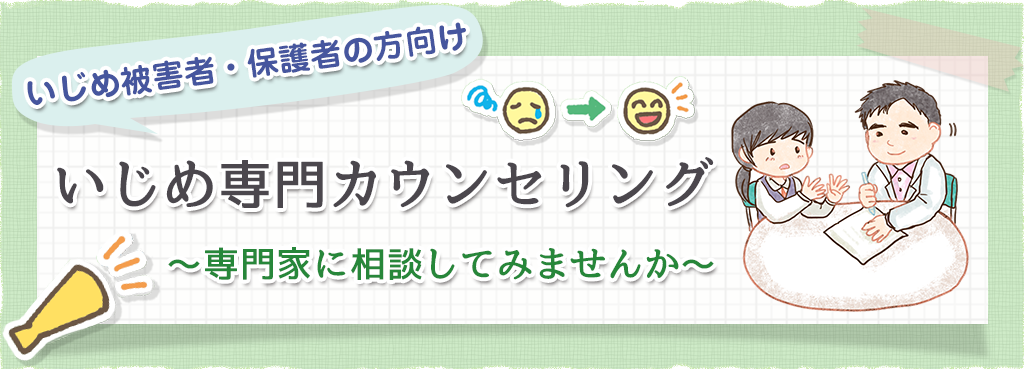~ いじめに関する法律 ~ いじめ加害者への処分は?退学・転校・指導の法的範囲を整理
はじめまして!いじめ撲滅委員会代表、公認心理師の栗本顕です。私の専門は「いじめ」です。心理学の大学院で研究もしてきました。現在はいじめの問題を撲滅するべく、研修やカウンセリング活動を行っています。今回のテーマは「いじめ加害者への処分は?退学・転校・指導の法的範囲を整理」です。

いじめの被害に遭ったお子さんを持つ保護者の方から「加害者はなぜ普通に学校に通えるのか」という声をよく聞きます。被害を受けた側が学校を休んだり転校したりする一方で、加害者が何事もなく過ごしている現実に納得できない気持ちは当然です。
本記事では、加害者への処分の法的な範囲と実際に学校ができることについて解説していきます。
目次は以下の通りです。
① 加害者への処分は現状では限定的
② 出席停止制度の実態と課題
③ 実際に使える指導の方法
④ 学校側の法的義務と責任
⑤ 私立学校の処分権限
⑥ 被害者保護の具体策
⑦ 加害者の責任追及方法
⑧ 今後の制度改善に向けて
いじめ問題の解決には、法律や制度の正しい理解が欠かせません。ぜひ最後までご一読ください。
加害者への処分は限定的
多くの保護者が期待する「加害者の退学や転校」は、実は法律上かなり制限されています。ここでは学校の種類ごとに、どのような処分が可能なのかを見ていきましょう。
公立小中学校は退学不可
公立の小学校と中学校は義務教育のため、法律で退学処分そのものが認められていません。これは加害者であっても、すべての子どもに教育を受ける権利があるという考え方に基づいています。
また、停学処分についても、公立・私立を問わず小中学校では実施できないことになっています。しかし実際の現場では「自宅謹慎」という名目で、事実上の停学措置が取られることもあります。
ただしこれも懲戒の意味合いがあれば違法となるため、学校側は慎重な対応を求められます。義務教育の段階では、加害者を学校から排除するのではなく、教育的な指導によって改善を図ることが法律の基本的な考え方です。

私立や高校の懲戒権
私立学校や高等学校では、退学処分を行うことが法律上は可能です。学校教育法に基づき、校長や教員には懲戒権が認められています。懲戒処分には退学、停学、訓告などがあり、いじめが深刻な場合にはこれらの処分が検討されます。
しかし実際には、退学処分を行うかどうかは学校側の判断に完全に委ねられています。多くの学校では、加害者やその保護者とのトラブルを避けるため、退学処分を差し控えるケースが少なくありません。
また、一度の違反行為で退学にすることは、最高裁の判例でも「最終手段」とされており、改善の機会を与える必要があるとされています。そのため実際に退学処分が下されることは極めて稀です。
被害者が転校する現実
現在の法制度では、いじめの加害者を強制的に転校させることはできません。これは加害者にも居住地に基づく就学権があるためです。その結果、いじめ被害に遭った子どもが恐怖や不安から学校に通えなくなり、転校を余儀なくされる一方で、加害者はこれまで通り学校生活を送り続けるという不均衡な状況が生まれています。
被害者の保護者からすれば「なぜ被害者が学校を去らなければならないのか」という怒りや悲しみは当然の感情です。この現実が、いじめ問題における最も大きな矛盾の一つとなっており、多くの保護者や教育関係者から制度改善を求める声が上がっています。
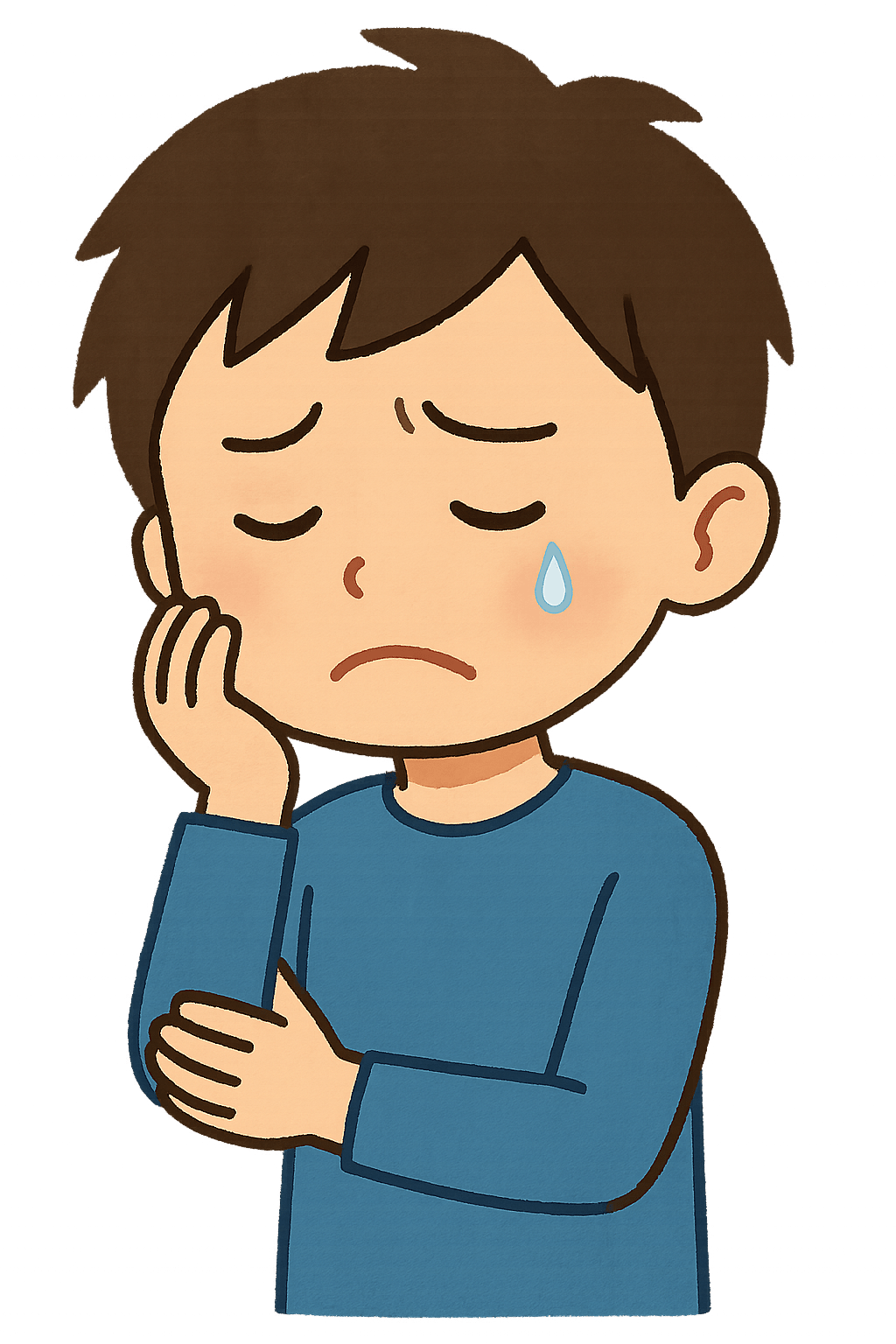
出席停止制度の実態
加害者への対応として「出席停止」という制度が法律で定められています。しかし実際にはほとんど使われていないのが現状です。なぜ使われないのか、その理由を見ていきましょう。
出席停止とは何か
出席停止とは、学校教育法第35条に基づいて市町村の教育委員会が加害児童の保護者に対して命じる措置です。この制度の目的は、懲戒処分とは異なり、
「学校の秩序を維持すること」
「他の児童生徒の教育を受ける権利を保障すること」
にあります。つまり加害者を罰するためではなく、被害者を含む他の子どもたちが安心して学べる環境を守るための措置なのです。
出席停止の期間中は、加害児童が学校に来ないことで被害児童の安全が確保され、その間に学校側と保護者が今後の対応について話し合うことができます。また、加害児童に対しては個別の指導計画を立て、学習の遅れが生じないように配慮することも求められています。
ほぼ使われない制度
文部科学省の統計によれば、2019年度の中学校におけるいじめ加害者の出席停止はなんと年間ゼロ件でした。全国で何十万件ものいじめが認知されているにもかかわらず、この制度はほとんど使われていないのです。
一方で、教師を対象にした調査では、中学校教員の約半数が「加害者を出席停止にすべき」と考えていることが明らかになっています。現場の教員も出席停止の必要性を感じながら、実際には実施できていない現実があります。
この背景には、手続きの複雑さ、前例の少なさ、そして教育委員会の及び腰な姿勢があると指摘されています。制度はあっても使われなければ意味がありません。
実施が難しい理由
出席停止が実施されない理由は以下になります。
加害者の教育権
証拠確保の困難
保護者対応の負担
事後フォロー必要
教育委の消極姿勢
まず、加害者にも教育を受ける権利があるため、その権利を制限するには相当な理由が必要です。また、いじめの証拠をしっかりと集めることも簡単ではありません。いじめは隠れて行われることが多く、明確な証拠がないと出席停止は命じられないのです。
さらに、加害者の保護者に説明したり、出席停止の期間をどれくらいにするか判断したりする負担も大きく、多忙な教育委員会にとって重荷となっています。出席停止期間中の加害児童へのフォロー体制も整備する必要があり、人員や予算の問題も絡んできます。
実際に使える指導の方法
出席停止が難しいとしても、学校には被害者を守り加害者を指導する方法があります。ここでは実際に学校で実施できる具体的な対応を紹介します。
別室指導の活用
いじめ防止対策推進法では、加害児童に対する「別室指導」が明記されています。これは加害児童を通常の教室から離れた別の部屋で個別に指導する方法です。別室指導のメリットは、被害児童の安全を即座に確保できることです。
加害児童が教室にいないことで、被害児童は安心して授業を受けられます。また、別室では教員が加害児童とじっくり向き合い、なぜいじめが起きたのか、相手がどれだけ傷ついているのかを考えさせることができます。
段階的に教室復帰を目指すこともでき、加害児童の反省の度合いや被害児童の気持ちを確認しながら、慎重に進めることが可能です。別室指導は出席停止よりもハードルが低く、学校の判断で実施できる現実的な方法です。

訓告などの懲戒処分
小中学校では退学や停学はできませんが「訓告」という懲戒処分は実施可能です。訓告とは、校長や教員が児童生徒に対して厳しく注意し、反省を促す処分のことです。
また、懲戒権の範囲内で認められる指導として、注意、叱責、居残り、別室での指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割り当てなどがあります。ただし、これらの指導は児童生徒に肉体的な苦痛を与えるものであってはなりません。
体罰は法律で明確に禁止されています。懲戒処分を行う際には、いじめの事実関係をしっかりと調査し、保護者にも十分な説明をすることが重要です。公平で適切な処分を行うことで、加害児童に自分の行為の重大性を理解させることができます。
クラス分けや接触制限
学校ができる配慮として、クラス分けの工夫や接触制限があります。一つの学年に複数のクラスがある場合、次年度のクラス替えで被害児童と加害児童を確実に別のクラスにすることができます。
また、教室も可能な限り離れた場所に配置することで、廊下などでの偶然の接触を減らすことができます。全校生徒が参加する運動会や文化祭などの学校行事では、必ず教員を両者に配置し、接触しないように見守る体制を作ります。
被害児童が「いつ加害者に会うかわからない」という不安を感じないような具体的な配慮が大切です。学校側は被害児童や保護者と丁寧に話し合い、どのような場面で不安を感じるのかを聞き取り、それに応じた対策を講じる必要があります。
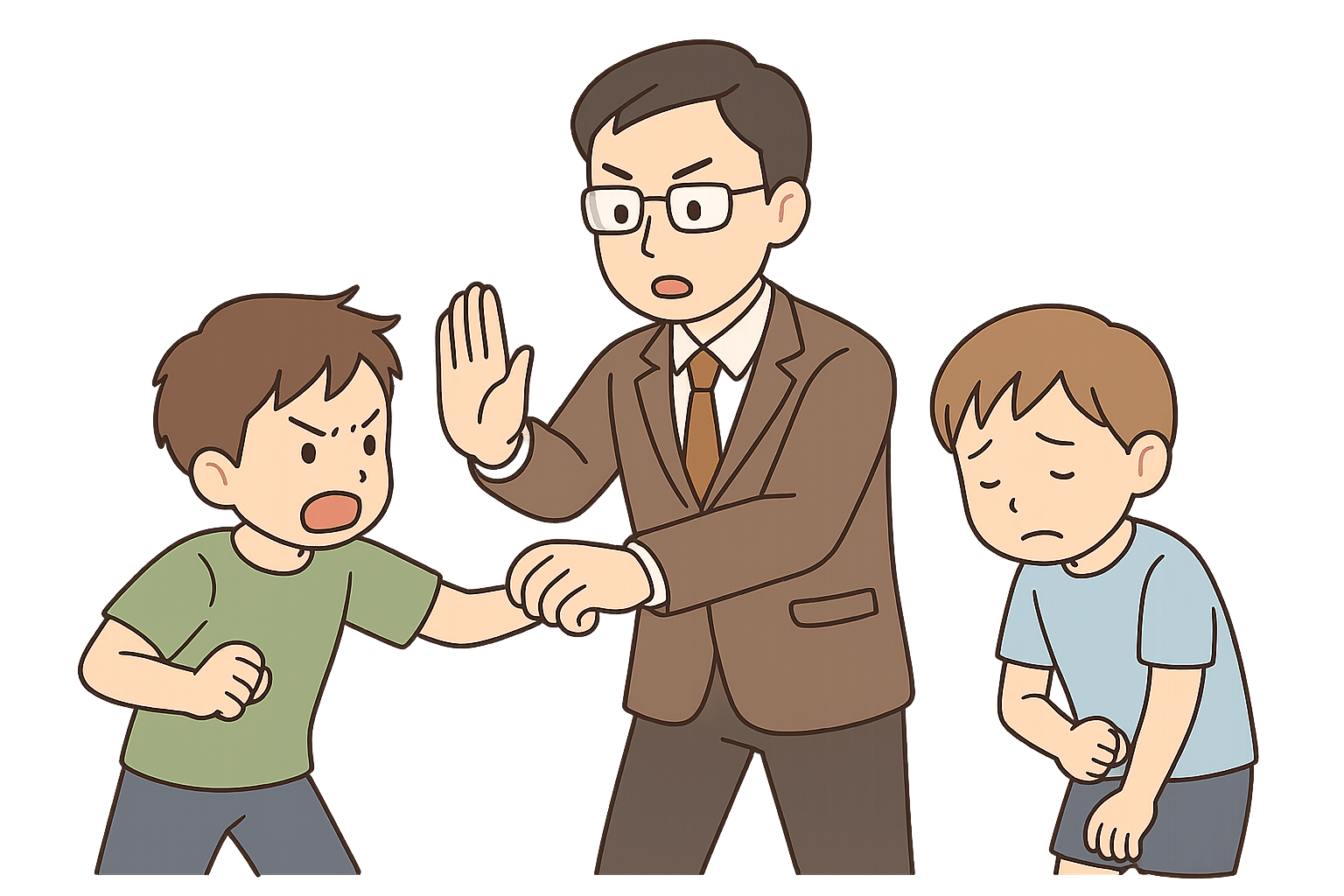
学校側の法的義務と責任
学校はいじめに対してどのような義務を負っているのでしょうか。法律で定められた学校の責任を理解しておくことが、適切な対応を求める上で重要です。
いじめ防止法の義務
いじめ防止対策推進法では、学校に対して明確な義務が定められています。義務の内容は以下になります。
事実確認と報告
被害児童の支援
加害児童の指導
保護者への助言
重大事態の調査
学校はいじめの事実を確認したら、速やかに学校の設置者に報告しなければなりません。また、被害児童とその保護者に対して適切な支援を行い、必要な情報を提供する義務があります。
加害児童に対しては教育的な指導を行い、その保護者にも家庭での指導について助言します。特に、いじめにより児童の生命や心身に重大な被害が生じた場合や、長期間の欠席を余儀なくされた場合は「重大事態」として、第三者委員会による詳細な調査が義務付けられています。

安全配慮義務とは
学校には、児童生徒の生命、身体、財産の安全に配慮する「安全配慮義務」があります。この義務の中には、いじめの被害をできる限り軽減する義務も含まれています。
もし学校がいじめを認識していながら放置し、適切な対応を取らなかった場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。
児童生徒や保護者からいじめの相談があったときに、教員が一人で抱え込んだり、「この程度ではいじめではない」と独断で判断したりすることは避けなければなりません。いじめの疑いがある場合は、必ず学校の組織として事実確認を行い、組織的に対応することが法律で求められています。学校の適切な対応が、被害の拡大を防ぐ鍵となるのです。
警察との連携基準
いじめの中には、明らかに犯罪行為に該当するものがあります。暴行罪、傷害罪、恐喝罪、器物損壊罪などは刑法で処罰される犯罪です。いじめ防止対策推進法では、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、学校は所轄の警察署と連携して対処しなければならないと定めています。
また、児童生徒に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察に通報する義務があります。「学校内の問題だから」と警察への連絡を躊躇してはいけません。
犯罪行為は犯罪として扱うことで、加害者に行為の重大性を認識させ、被害者の権利を守ることができます。学校と警察が適切に連携することが、深刻ないじめへの対応には不可欠です。
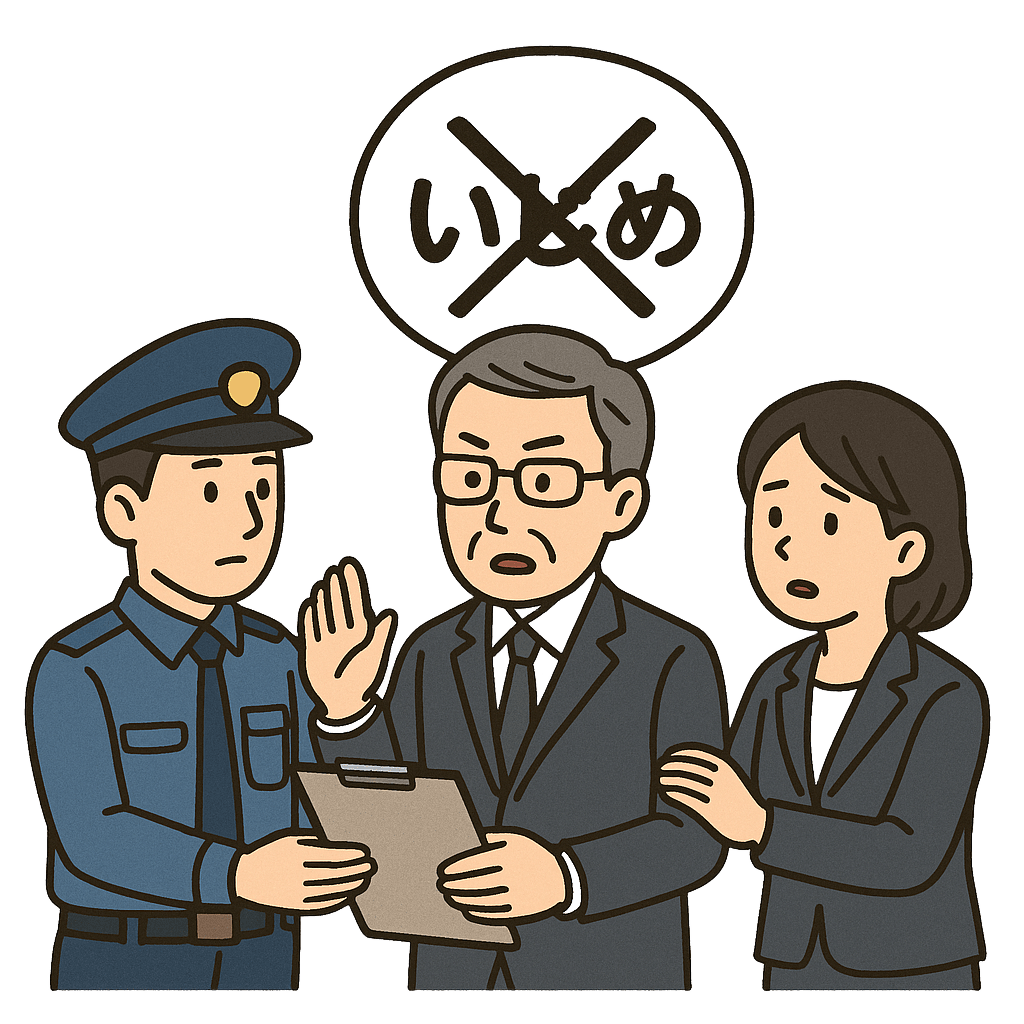
私立学校の処分権限
私立学校は公立学校とは異なる処分権限を持っています。私立学校特有のルールと限界について理解しておきましょう。
私立の退学基準
私立の小学校と中学校は、公立とは異なり退学処分を行うことが法律上可能です。ただし停学処分は、公立と同様に実施できません。私立学校の退学基準は学校教育法に基づいており、一般的には、
性行不良で改善の見込みがない者
学力劣等で成業の見込みがない者
正当な理由なく出席常でない者
学校の秩序を乱した者
などが退学事由として定められています。
いじめ行為は「学校の秩序を乱す行為」や「他の児童生徒に危害を加える行為」として、退学処分の対象となる可能性があります。しかし実際には、私立学校でも退学処分は慎重に判断されており、よほど悪質で改善の見込みがない場合に限られます。
退学は最終手段
最高裁判所の判例では、退学処分について重要な基準が示されています。それは「当該生徒を学校内に留め置くと学校の秩序が保てないという最終的な場合にやっと退学が認められる」というものです。
つまり退学は、他にどのような手段を取っても問題が解決できない場合の最終手段なのです。一度の違反行為で即座に退学にすることは、この基準に照らして認められません。
学校は違反行為の内容や性質、生徒の反省の度合い、改善の可能性などを総合的に考慮する必要があります。たとえいじめ行為があったとしても、生徒が深く反省していて、被害者との和解の可能性がある場合には、退学以外の方法で指導することが求められます。退学は生徒の教育を受ける権利を奪う重大な処分だからです。
私立の出席停止措置
出席停止制度は、学校教育法で「市町村の教育委員会」が行うものと定められているため、私立学校には直接適用されません。しかし、私立学校にも児童生徒に安心して学べる環境を提供する義務があります。
そのため法律の趣旨を踏まえれば、私立学校でも学校秩序を維持するために一時的に加害児童の出席を制限することは可能と解釈されています。ただし注意が必要なのは、この措置が懲戒の意味合いを持つ場合は違法となる点です。
あくまでも「被害児童を守るため」「学級環境を整えるため」という目的で、一時的に行われるものでなければなりません。私立学校は独自の校則を持ちますが、その運用も教育的配慮と法律の範囲内で行うことが求められています。
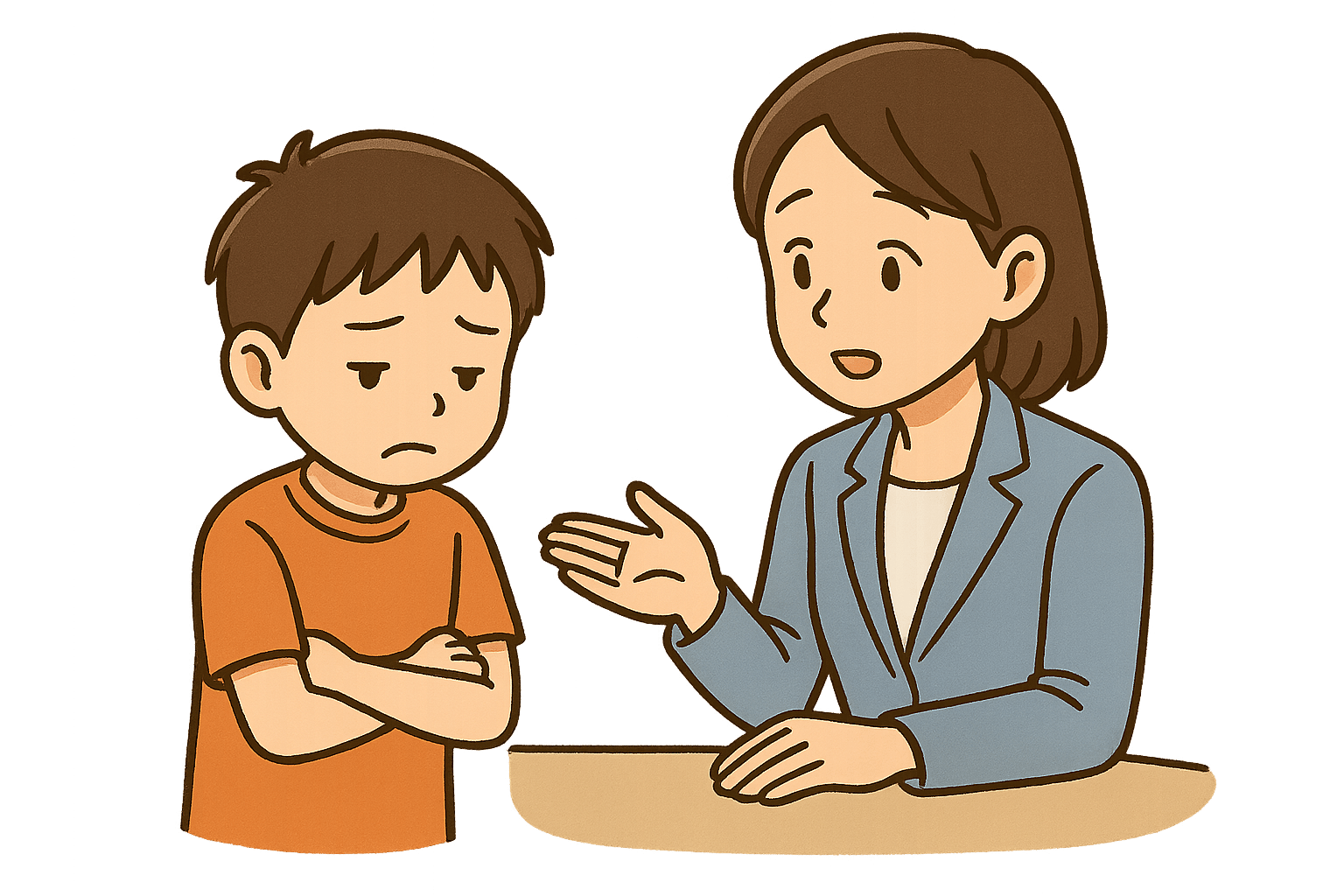
被害者保護の具体策
加害者への処分が難しい現実がある中で、被害者をどう守るかが最も重要です。被害者とその家族が取れる具体的な保護策を見ていきましょう。
被害者の転校支援
いじめ被害を理由に転校することは、教育委員会への申し立てによって認められる可能性があります。通常、公立の小中学校に通う場合は、住民票のある市区町村が指定する学校に通わなければなりません。
しかし、市区町村の教育委員会が「相当と認める」場合は、指定校以外の学校への転校が可能です。多くの市区町村では、いじめやいじめによる不登校などが発生していて、指定校以外の学校へ就学することで問題解決が見込まれる場合には、転校を認めています。
文部科学省も、いじめを受けた児童生徒や保護者が希望する場合には、時期にかかわらず転校について弾力的な対応を検討するよう求めています。転校は被害児童の心の回復にとって有効な選択肢の一つです。
転校費用の賠償請求
いじめが原因でやむを得ず転校した場合、その転校にかかった費用を損害として賠償請求できる可能性があります。請求先は以下になります。
加害者本人
加害者の保護者
学校の設置者
担当教職員
ただし、転校費用が認められるためには、いじめと転校との間に「相当因果関係」が必要です。つまり、いじめがあったから転校せざるを得なかったという因果関係を証明しなければなりません。
そのためには、いじめがあったことを示す証拠が重要になります。学校とのやり取りの記録、医師の診断書、いじめの具体的な内容を記録したメモや写真などを残しておくことが大切です。
相手がいじめを認めず裁判に発展した場合、第三者から見てもいじめがあったとわかる客観的な証拠が必要になります。
心のケアと支援
いじめ被害を受けた子どもには、心のケアが何よりも重要です。多くの学校にはスクールカウンセラーが配置されており、専門的なカウンセリングを受けられます。
スクールカウンセラーは臨床心理士や公認心理師などの資格を持つ専門家で、子どもの心の傷に寄り添い、回復を支援してくれます。また、医療機関を受診して適応障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの診断を受けることも、被害の深刻さを示す重要な証拠になります。
診断書は学校への説明や、場合によっては法的な手続きにおいても役立ちます。何よりも大切なのは、継続的な見守りと、子どもが安心して過ごせる環境を作ることです。焦らず、子どもの気持ちに寄り添いながら、ゆっくりと回復を待ちましょう。
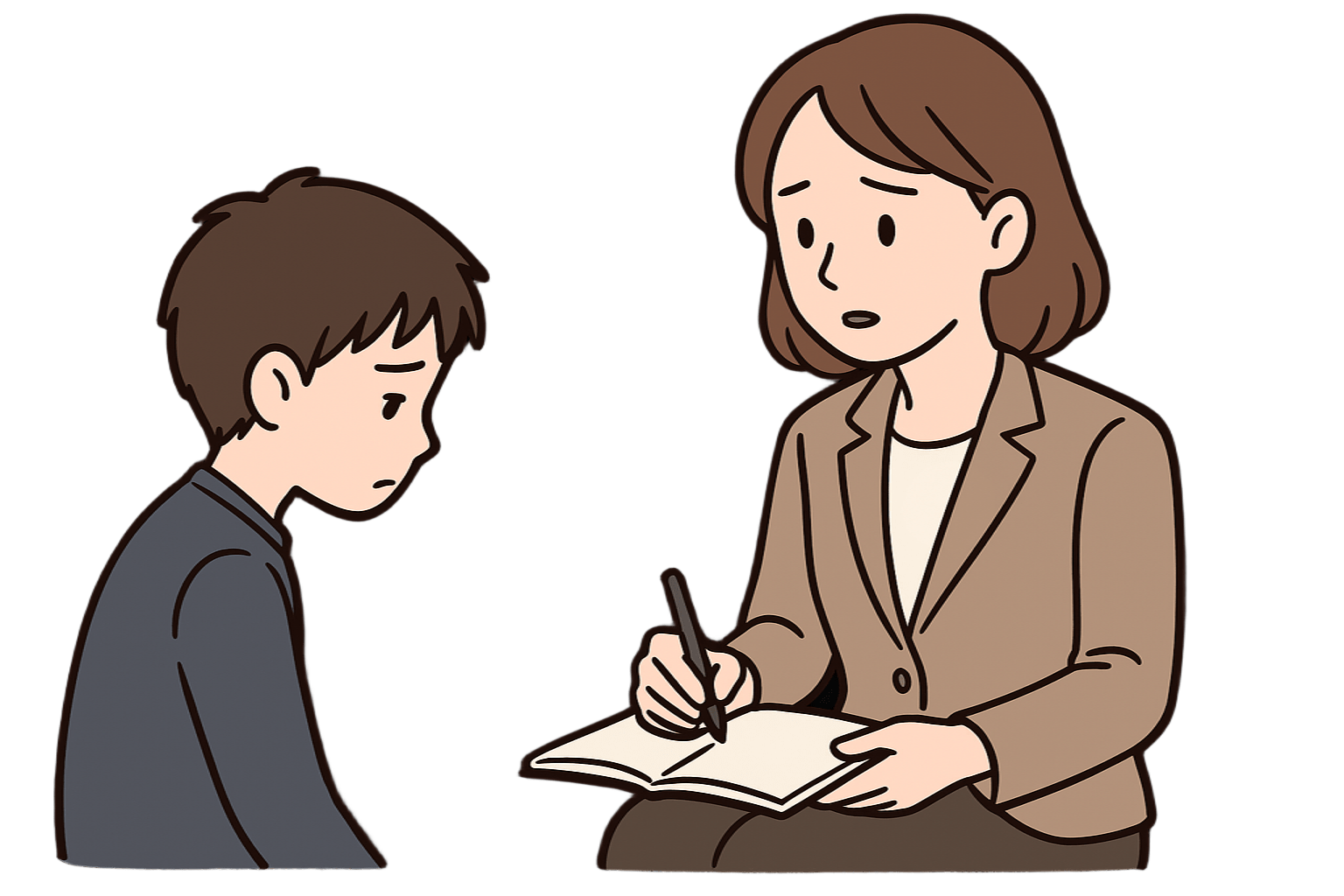
加害者の責任追及方法
いじめ被害に対して、加害者側の責任を追及する方法もあります。民事と刑事、それぞれのアプローチについて理解しておきましょう。
民事上の損害賠償
いじめによって被害を受けた場合、民事上の損害賠償を請求することができます。請求の相手は、加害者本人またはその保護者です。もし加害者に責任能力がない場合(一般的には12歳未満)は、民法により保護者などの監督義務者が損害賠償責任を負います。
損害賠償の対象となるのは、慰謝料、治療費、転校費用、カウンセリング費用などです。損害賠償請求を行う際には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、被害者側の精神的負担を軽減できますし、加害者側も冷静に話し合いに応じやすくなります。
示談が成立すれば、謝罪と賠償によって一定の区切りをつけることができます。ただし、お金の問題だけでなく、真摯な謝罪と再発防止が何より重要です。
刑事告訴の可能性
いじめ行為の中には、刑法上の犯罪に該当するものがあります。たとえば、殴る蹴るなどの暴力は暴行罪や傷害罪、お金を脅し取る行為は恐喝罪、持ち物を壊す行為は器物損壊罪に当たります。
ただし、刑事責任を問えるかどうかは年齢によって異なります。14歳未満の子どもは刑事責任を問われないため、警察に逮捕されることはありません。このような子どもは「触法少年」と呼ばれ、児童相談所が対応します。
一方、14歳以上の場合は刑事責任を問われる可能性があり、少年法による手続きが取られます。悪質な事件では家庭裁判所に送致され、少年院送致などの処分が下されることもあります。
刑事事件として扱うことで、加害者に行為の重大性を認識させる効果があります。

学校や教員の責任
いじめについて、学校や教員の責任を追及することもできます。責任の根拠は以下になります。
安全配慮義務違反
監督義務の懈怠
適切な対応欠如
情報共有の不足
公立学校の場合は、国家賠償法に基づいて学校の設置者(国や地方公共団体)に損害賠償を請求します。教職員個人は原則として責任を負いませんが、故意や重大な過失があった場合は別です。
私立学校の場合は、学校法人に対して使用者責任または安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求できます。また、教職員個人に対しても、不法行為責任を追及できる場合があります。
学校の責任を問うには、学校がいじめを認識していたか、認識し得たかという点と、適切な対応を取ったかどうかが重要な争点になります。
まとめ
いじめの加害者への処分は、法律上かなり制限されているのが現実です。公立の小中学校では退学も停学もできず、出席停止制度もほとんど使われていません。その結果、被害を受けた子どもが学校を離れ、加害者が何事もなく学校生活を送り続けるという不均衡が生じています。この現実に対して、保護者が怒りや悲しみを感じるのは当然のことです。
しかし、諦める必要はありません。別室指導やクラス分けなど、学校ができる対応はあります。また、いじめ防止対策推進法により、学校には明確な義務が課されています。学校が適切に対応しない場合は、教育委員会への相談や、弁護士への依頼も検討しましょう。
相談をご希望の方へ
いじめ撲滅委員会では、全国の小~高校生・保護者のかた、先生方にカウンセリングや教育相談を行っています。カウンセラーの栗本は、「いじめ」をテーマに研究を続けており、もうすぐで10年になろうとしています。
・いじめにあって苦しい
・いじめの記憶が辛い
・学校が動いてくれない
・子供がいじめにあっている
など、いじめについてお困りのことがありましたらご相談ください。詳しくは以下の看板からお待ちしています。