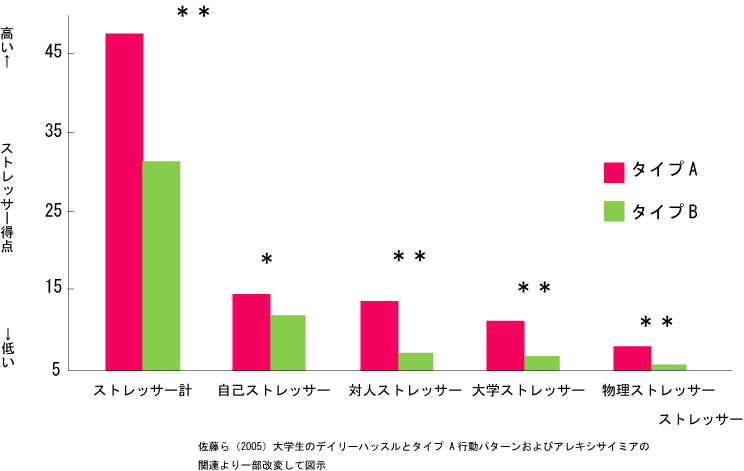アンガーマネジメント入門‐意味,方法
皆さんこんにちは。公認心理師の川島達史です。私は現在、心理学の講師としてこちらの心理学講座で活動しています。今回のテーマは「アンガーマネジメント」です。

目次は以下の通りです。
コラム1.アンガーマネジメント入門・意味
コラム2.怒りの段階確認法,マインドフルネス
コラム3.相手への期待値を下げる
コラム4.アンガーマネジメントの資格・講座
怒りのコントロールは極めて重要です。なぜなら、離婚、別れ、虐待、DV、パワハラ、犯罪、戦争、これらの原因のほとんどに怒りが関連しているからです。
怒りをコントロールできるようになれば、人間関係のトラブルも起きづらくなり、大事な人たちと平穏で豊かな生活を送る助けになると言えます。是非最後までご一読ください。
意味と歴史
意味
アンガーマネジメントには様々な意味があります。
怒りを予防・制御するための心理療法プログラム 不適切な怒りの感情をうまくコントロールすることを目指す
(Novaco, 1975)[1]
“感情”の中でとくにマイナスな結果を引き起こす原因となる“怒り”に正しく対処することで、健全な人間関係をつくり上げる知識・技術を習得するということ
(安藤,2015)[2]
怒りを感じること自体は自然なことですが、その表現方法が問題になることがあります。アンガーマネジメントでは、怒りの原因を理解し、冷静に対応する力を養います。
歴史
アンガーマネジメントは、1970年代のアメリカで本格的に広がっていきました。第1人者は心理学者のRaymond Novacoです[3]。
Novacoは1975年、「怒りを予防・制御するための心理的対処力」を提唱し、アンガーマネジメントをモデル化しました。その後、怒りの管理の重要性が認識され、犯罪者、精神疾患、ビジネス分野、教育分野で導入されるようになりました。

1991年になると、Michael Jeffreyが「攻撃性と怒りの管理」において、怒りの発生メカニズムとその管理法を探求しました。具体的には、認知行動療法とリラクゼーション技法を組み合わせたアプローチを強化し、怒りの管理におけるストレス軽減技術の重要性を強調しました[4]。
2001年には、 Novacoと共同研究者は、受刑者を対象にしたアンガーマネジメントプログラムの効果を検証しました。この研究では、怒りのコントロールが犯罪行動の減少に寄与することが明らかになり、アンガーマネジメントの重要性が強調されました。この成果により、刑務所や法的場面でのアンガーマネジメントが広がり、再犯防止のための有効な手段として認識されるようになりました。
日本では、文部科学省(2011)[5]が「アンガーマネジメントを感情理解教育」とし、児童・生徒のうちから学ぶべきスキルとして推奨しています。また、グーグルでの月間検索数は50,000件前後となっていて、需要が増加しています。
一方で、日本の研究はアメリカほど盛んではありません。例えば、論文検索サイトでは500件前後とやや少ない状況で、学会での精査もまだまだと言えます。怒りのコントロールの重要性を考えると、今後は日本でも研究数が増えていくと予想できます。

怒りと体の仕組み
私たちが怒るときは、体の中で様々なプロセスが起こっています。まず初めに怒りと体の仕組みについて考えてみましょう。
①怒りの外部刺激を受ける
外部刺激とは、怒りを引き起こす要因のことで、たとえば侮辱を受ける、不公平な扱いを受ける、誤解をされる、金品を奪われそうになる、などが該当します。これらの刺激に直面すると、脳は即座に反応し、感情的なプロセスが始まります。
②扁桃体が反応する
怒りのきっかけとなる外部刺激を受けると脳内の「扁桃体(へんとうたい)」が反応します。扁桃体は、感情・情緒,すなわち怒り、恐怖、不安を感じる脳の部位で、原始的な脳と言われています。ヒトは危機を感じると、扁桃体が活発になり、合理的な判断がしにくくなります。

③ホルモン量が変化する
扁桃体が反応すると、ホルモンの量が変化していきます。例えば、ノルアドレナリンが放出され、ストレス反応を引き起こし、身体を緊張させます。また、アドレナリンが増え、 怒りを感じると同時に、心拍数を上昇させ、エネルギーを増加させます。さらには、コルチゾールが放出され ストレスホルモンが分泌され、身体のストレス反応を促進します。
④交感神経が活性化する
怒りに関連するホルモンが放出されると「自律神経」が対応を始めます。自律神経には2種類あり、それぞれ以下のような働きがあります。
*交感神経
緊張する、活力を上げる、心拍数が上がる
*副交感神経
リラックス、休息する、心拍数が下がる
怒りを感じている時、体は「交感神経」が優位になりす。例えば、心臓の鼓動が早くなり、血流や血圧が高まったりします。これは体が戦いの準備を始めているサインになります。うまく制御できないと、カッとなり、暴言や暴力へと発展していきます。
怒りと心理的な影響
現在の生理学、心理学的な研究によると、怒りには様々なマイナスの影響があることがわかっています。以下に研究を折りたたんで記載しました。興味のある研究がありましたら展開してみてください。

アンガーマネジメント手法8つ
ここからは、アンガーマネジメントのやり方を8つ提案させて頂きます。
①マインドフルネス力をつける
②関係ないこと話す方
③怒りの段階確認法
④リラックス深呼吸法
⑤相手への期待値を下げる
⑥認知療法,考え方を増やす
⑦心に余裕を持つ
⑧体の状態を整える
ご自身にあった内容を組み合わせてご活用ください。
①マインドフルネス力をつける
アンガーマネジメントの基本は「怒りに気がつく」ことです。なぜなら、怒りに気がつくと「いま私は怒っている…このまま暴言を吐いたら取り返しがつかない…」と行動を冷静に判断することができるからです。
「気がつく力」をつけるには、マインドフルネス療法を学ぶことをおすすめします。マインドフルネスとは、「今この瞬間の状態・体験・感情など、あるがままの自分に気づくこと」を意味します。この感覚を身につけると、自分の感情や価値観を客観的に把握することができるようになります。
マインドフルネスには様々な手法があります。一例として、簡単な手法をご紹介します。
頭の中に何か浮かんだとき、「〇〇になっている自分がいるな」と確認・観察します。具体的には以下のように観察していきます。
遅刻されて怒っている自分がいるな…
手伝ってくれないとイラつく自分がいるな…
約束を破られてムカつく自分がいるな…
このとき、「こう思うのは悪いことだ」といった価値判断を下さずに、「今こういう感情を持っているんだな」と、その感情をただ観察して、その場に置いておくようにします。このように自分を観察する練習をしていくことで、感情に巻き込まれず、冷静になることができます。
マインドフルネスについては、以下のコラムで詳しく解説しています。理解を深めたい方は参考にしてみてください。

②関係ないこと話す方
怒りと距離を置く上で、重要なのが全く関係ないワードをはさむことです。少しイメージしづらいかもしれませんので、以下に例を用いて解説していきます。
怒りワード
「絶対に許せない!」
・
関係ないワード
「かっぱ寿司食べ放題」
・
怒りワードに関係ないワードをはさむ
「絶対に許せない!かっぱ寿司食べ放題♪」
「絶対に許せない!かっぱ寿司食べ放題♪」
いかかでしょうか。このように怒りから生まれる考えや言葉に、まったく関係ないワードをはさむことで、その怒りから距離を取ることができます。
コツとしては関係ないワードをはさむときは、具体例のようになるべく明るいワードにするようにしましょう。暗いフレーズを使うと、効果が薄れてしまう可能性があります。
以下練習問題を作成しました。より体験的に理解したい方はぜひチャレンジしてみてください。
③怒りの段階確認法
マインドフルネスができるようになると、自分の状態を確認する力がついていきます。「怒り」感情は、ピークの状態になる前に様々な段階を踏むことが多いです。具体的には、以下の6段階でステップアップしていきます。
ステップ1 疑惑 疑問
ステップ2 困惑 戸惑い
ステップ3 不満 納得できない
ステップ4 ムカつく イライラする
ステップ5 怒り カッとなる
ステップ6 暴力 暴言
怒りをコントロールするには、早めの段階で気がつくことが大事です。
例えば、「ステップ2 困惑」の段階にあるとします。この時、自分の体の状態を観察すると落ち着きやすくなります。
いま自分は困惑の段階にいるな…
少し呼吸が荒くなっている…
ゆっくり呼吸をしよう…
と考えると、怒りを抑制することができます。段階を確認し、気持ちを落ち着ける手法は以下のコラムで解説しました。理解を深めたい方は是非ご参照ください。
④リラックス深呼吸法
深呼吸法は感情コントロールの王様です。是非マスターしたいところです。以下の手順で落ち着きを取り戻してください。
①吸う
5秒程度、鼻から息を吸います。
この時、リラックスした空気が体を循環するイメージをしましょう。
②止める
2秒程度息を止めます
③吐く
10秒程度かけて、口から息を吐きます。
この時「ムカつく気持ち」が体の外に出ていくイメージをしましょう。
この手順を、気持ちが落ち着くまで何度か繰り返します。
いかがでしょうか。これだけでも、暴言や暴力などの極端な行動を予防することができます。怒りを感じたらまずは深呼吸を原則としてみてください。
「感情的になったらまずは深呼吸!」と覚えておきましょう。詳しくは以下のコラムで練習してみてください。
⑤相手への期待値を下げる
人間関係において、怒りっぽい人もいれば、穏やかな人もいます。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。1つの特徴として、怒りやすい人は周りの人への期待値が高いという特徴があります。
例えば、「相手に期待したうちの何%が結果として返ってきたか」によって、感情はこのように変化します。

このように、期待していた結果を下回れば下回るほど、イライラや怒りの感情が抑えられなくなります。期待値が高いほど相手のハードルも上がってしまうため、「期待値が高いほどイライラする結果になる可能性が高くなる」というわけです。
怒りをコントロールする1つのコツとして、「高すぎる期待を現実的なレベルに下げていく」という手法があります。例えば、以下のように相手への期待を下げると効果的です。
どんな時でも時間は厳守すべきだ!
→プライベートでは多少ゆるくてOK
仕事ではメールを必ず返すべきだ!
→たまには忘れてしまうこともある
このように「○○してくれたらいいな」ぐらいの期待感にとどめておくと、他人に対して寛容になり、怒りも感じにくくなります。他人に対して強い口調で怒ってしまう…と感じる方は以下のコラムを参照ください。
⑥認知療法,考え方を増やす
アンガーマネジメント力をつけるには、認知療法がおすすめです。認知療法とは以下の意味があります。
極端な考え方を見直し、健康的な考え方をふやす事でメンタルヘルスを安定させる手法
怒りをうまく制御できない人は、思考の偏りがあり、感情が極端になりがちです。この点、認知療法を学ぶと考え方の幅が広がり、怒りのコントロールがしやすくなります。
認知療法はアンガーマネジメント力と相性が良いので、お時間はある時にぜひ学んでみてください。
⑦心に余裕を持つ
細田ら(2009)[10]は、中学生305名を対象に、ソーシャルサポートと自他への肯定感に関する研究を行いました。その結果、自己肯定感が下がると、他者肯定感も下がることが分かりました。

上図のように自己肯定感と他者肯定感は、相関関係にあります。つまり、自分を否定的に見る人は、他人も否定的に見てしまう傾向があるのです。
自分を肯定する力が不足している方は、心の余裕がなくなりやすく、相手にイライラしやすくなります。これに対して、自己肯定感がしっかりあり、心に余裕がある方は、相手を許す寛容さを持ち合わせています。普段から自分の心も豊かにしておくように心がけましょう。
自己肯定感が不足している…と感じる方は以下のコラムを参照ください。

⑧体の状態を整える
生理学や心理学の研究では、身体にストレスがかかると怒りやすくなることがわかっています。怒りは身体の状態と密接にかかわります。
例えば寝不足の時は誰でもイライラしやすく、ちょっとしたことで怒りっぽくなってしまいます。対策としては以下を心がけてください。
充分な睡眠
日光を浴びる
適度に運動する
森林浴をする
栄養バランスをよくする
体が健康で快調だと、心も穏やかに過ごしやすくなります。以下のコラムでは、日常的な体のストレスを軽くする手法を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
今回はアンガーマネジメントの手法について詳しく解説していきました。怒りは私たちの人生を壊しかねない強烈な感情です。
もし怒りを感じたら、まずはその感情に気がつき、深呼吸をしたり、考え方を柔軟にすることで、いつもの自分を取り戻すようにしましょう。皆さんが心穏やかに、健康的な人間関係を築かれることを願っています。
資格,学校の種類
アンガーマネジメントをより深く学びたいという方は、講座・資格の勉強をお勧めします。アンガーマネジメントを学べるスクールは様々ありますが、その中でも特におすすめなものを、コラム④で取り上げています。アンガーマネジメントの講座・資格を知りたい方は下記をご覧ください。
しっかり身につけたい方へ
当コラムで紹介した方法は、公認心理師による講座で、実際に学ぶことができます。内容は以下のとおりです。
・アンガーマネジメントの手法
・ムカつく心理の改善,認知療法
・イライラする考え方の改善
・感情コントロール,マインドフルネス療法
講師に質問をしたり、仲間と相談しながら進めていくと、理解しやすくなります。🔰体験受講🔰に興味がある方は下記の看板をクリックください。筆者も講師をしています(^^)
監修
名前
川島達史
経歴
- 公認心理師
- 精神保健福祉士
- 目白大学大学院心理学研究科 修了
取材執筆活動など
- NHKあさイチ出演
- NHK天才テレビ君出演
- マイナビ出版 「嫌われる覚悟」岡山理科大 入試問題採用
- サンマーク出版「結局どうすればいい感じに雑談できる?」
YouTube→
Twitter→

名前
長田洋和
経歴
- 帝京平成大学大学院臨床心理学研究科 教授
- 東京大学 博士 (保健学) 取得
- 公認心理師
- 臨床心理士
- 精神保健福祉士
取材執筆活動など
- 知的能力障害. 精神科臨床評価マニュアル
- うつ病と予防学的介入プログラム
- 日本版CU特性スクリーニング尺度開発

名前
亀井幹子
経歴
- 臨床心理士
- 公認心理師
- 早稲田大学大学院人間科学研究科 修了
- 精神科クリニック勤務
取材執筆活動など
- メディア・研究活動
- NHK偉人達の健康診断出演
- マインドフルネスと不眠症状の関連